はい!みなさん、こんにちは!
事務局の渡辺です。
今回は鍼灸校の光澤先生たちと共に作成しました。
緑の眩しい季節となりましたね!
さくら通りの桜も既に青葉若葉輝く葉桜へと変わり
燃え立つような満開のツツジが出迎えてくれています。

吹く風の小気味のいい音と
寒からず暑からずのよき季節。
そして、GWという名の連休。
1年中、5月だったらいいのに……
と思うのは私だけでしょうか。
心が弾む季節となり、
屋根よりも高い鯉のぼりを見ながら新茶を飲む……
そんなことを想像しながらブログを打ち込んでおります。
鯉のぼりの由来
挨拶で“鯉のぼり”と出しましたが
ここ最近では五月人形と共に飾る家を見なくなりましたね。
(住宅事情や防犯意識の変化、他にも少子化とかいろいろありそうですね……)
個々人で見る機会は減りましたが
一行事やイベントとして行う地域は多いです。
都内でも、東京タワーや東京ミッドタウンにて鯉のぼりの展示などが開催されているため
この機会に見に行ってみることをオススメします!
そして、「鯉のぼり」には、男児の成長と出世を願う意味があります。

中国の故事である、竜門という滝を登った鯉が竜となって
天に昇った「登竜門」伝説にちなみ、立身出世を願います。
また鯉は、
池や沼など環境の整っていない状況でも生きていける生命力の強い魚なので
「どんな環境でもたくましく成長し、立派になってほしい」
という願いが込められているとのことです。
「ブリ」や「カツオ」など出世魚でお祝い
「ブリ」や「カツオ」など縁起のよい魚!
端午の節句は、男の子の健康や成長を願う日です。
成長段階によって名前が変化する「出世魚」のブリは、
男の子の成長を祝う日の食べ物にふさわしいといえます。
ブリはスーパーなどで入手しやすく
切り身を買えば家庭でも調理しやすいというメリットがあります。
ブリを使った料理としては、ブリ大根やブリの照り焼きが定番です。
また「勝つ男」という意味で縁起のよいカツオも、人気の食べ物です。
カツオといえば、タタキですね。


~余談【昔の人はダジャレが好きだったのか?】~
端午とは、細かくいうと「月の端(はじめ)の午(うま)の日」となります。
午とは干支に出てくる十二支のうちの一つです。
私たちはその年の干支ばかり注目しがちですが
暦では月にも日にも干支が設定されています。
その後、「午(うま)」を「ご」と読むことから毎月5日が「端午」に固定されました。
さらに「ご」が重なる5月5日を特別に端午の節句と呼ぶようになったと言われています。
また、端午の節句そのものは病気や悪い出来事を避けるための行事の日で
薬草を摘み、厄除けの菖蒲を飾るだけでした。
とくに男の子のお祝いするといった特別な日ではなかったそうです。
鎌倉から武士の時代へと移り変わっていく中で
男の子に兜や刀を贈る習慣が広まったそうです。
現在は人形ですが、当時は本物の兜だったそうですよ。
これは、菖蒲(しょうぶ)を勝負や尚武(武道を大切にする考え方)に
引っ掛けて男の子の節句に変化していったと考えられていたそうでして……

カツオが「勝つ男」であるように、日本の歴史を調べると
このようなダジャレというか語呂合わせが多いですね……。
五月病や疲れに負けないように手のひらを太陽へ
これからGWです!
光澤先生からオリジナルの呼吸法を皆さんに伝授してくれるそうです!
「手のひらを太陽に」の運動が体と心をリフレッシュしてくれます!
♪僕らはみんな生きている ☞ 手のひらを胸に猫背の姿勢で息を吐く

♪生きているから歌うんだ ☞ 息を吸って手を前に出して大きく吐く
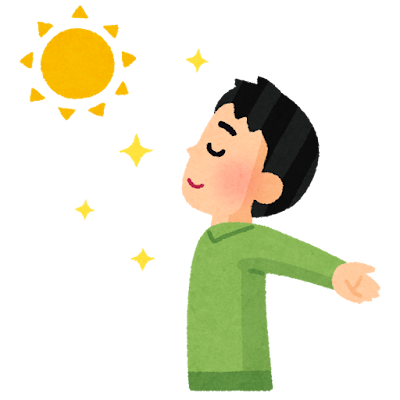
♪手のひらを太陽に透かして見れば
☞ 両手を上にあげて太陽を見るように手に平を返す
顔が上がって視野が広がり、胸を開いて大きく息が吸える

♪真っ赤に流れる僕の血潮 ☞ 手のひらを上にお腹の前に下ろす

4月は新生活で頑張って、5月に心身の疲れが出る頃。
疲れた姿勢は猫背で胸が詰まって頭も下がり
暗く感じて息もうまく吸えない状態になります。
手のひらを太陽にかざすことで頭が上がり、胸が開きます。
お腹の前で手のひらを上に向けて呼吸をすると
顔が上がって楽に息が吸えます。
逆に
手のひらを下にして呼吸すると息が詰まり
視線も下がります。
東洋医学では
肺は魄(人の肉体に宿り、活力を生み出すもの。魂。)が宿るとされ
手のひらを上に息をすることは、肺につながる経路が開いて全身に気血が巡り
塞いだ気分も晴れていくそうです。
「手のひらを太陽に」の運動をゆっくりとした動きで
やってみると気分が落ち着いて、ゆとりが生まれてきます。
疲れた時は是非、お試しください。

.jpg)
-1.jpg)
