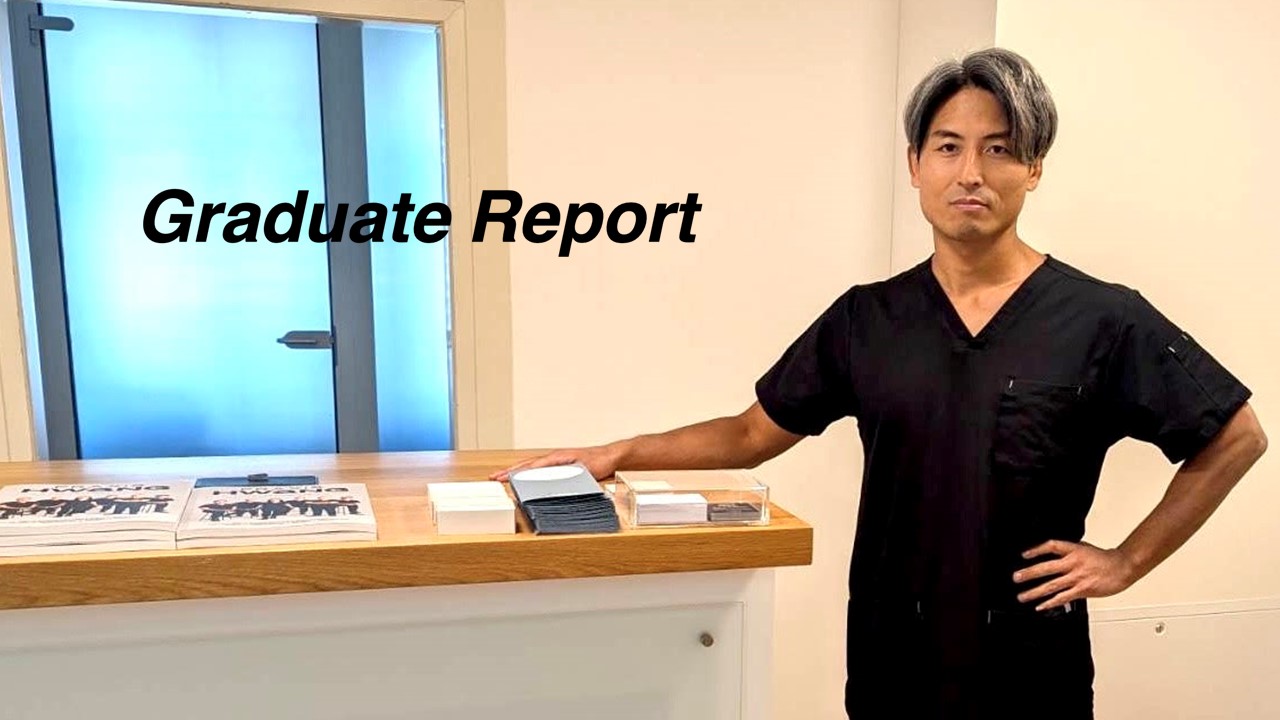東洋医学研究班 👉👉👉 脈診班
日本鍼灸理療専門学校 教員の橘です。
今回は脈診班について、東垣先生にインタビューしながらご紹介します。
私も2008年ごろ・・・脈診班に所属していました。懐かしいです。
東洋医学研究班は、脈診班とも呼ばれていますので、
ここでは脈診班と呼ばせてもらいます。
まず「脈診」とはなに?
私たちはからだの具合を診断するために四診(ししん)という方法を用います。
四診とは
「望診(ぼうしん)」:目で見て情報を集める方法。
「聞診(ぶんしん)」:音や匂いから情報を集める方法。
「問診(もんしん)」:質問をして情報を集める方法。
「切診(せっしん)」:触ることで情報を集める方法。
の四つですが、切診のなかには手首の拍動(脈)を施術者の指で診て、
からだの状態を確認する方法があります。それが、脈診です。
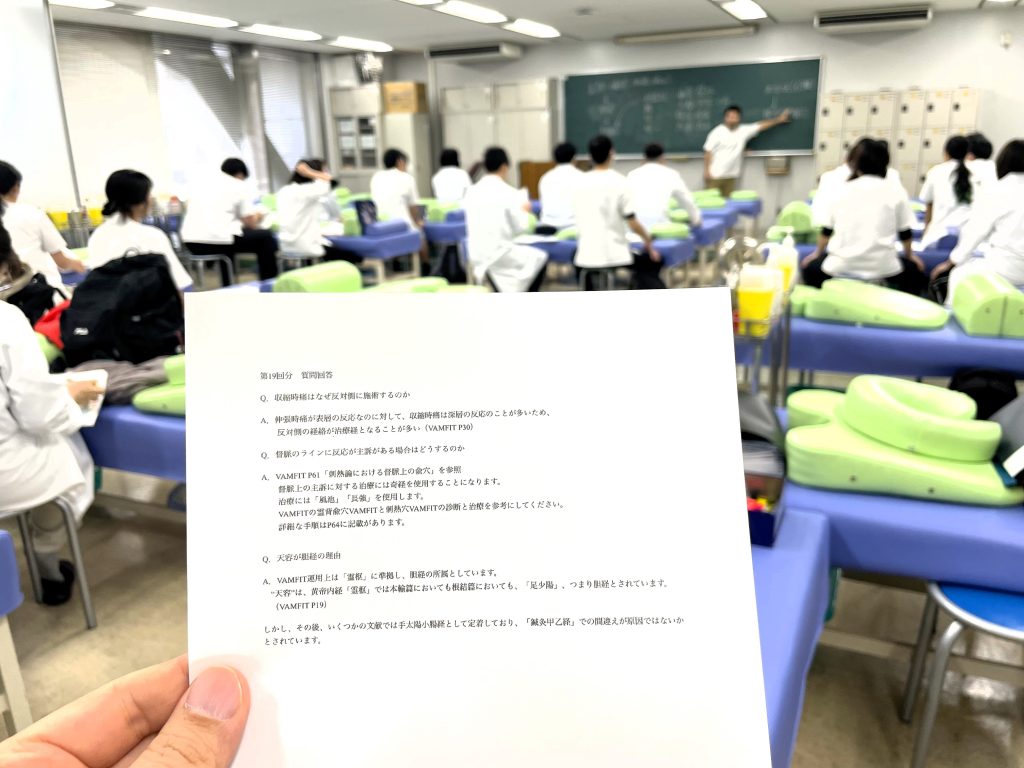
活動日時は
毎週木曜日 12時50分 ~14時
橘🎤
脈診班の活動はどんなものですか?
東垣🗣️
東洋医学の脈診は診察のみならず、
脈の状態で治療法まで導き出され、
効果の判定にも用いられます。
その脈診を研究することが大きなテーマですが、
そのためにはまず脈診を身に付けることが必要で、
脈診を修得するための活動でもあります。
脈診ができるようにするためには、
どんな工程を踏んで、日々どんな練習をすればいいのか、
習得するためのプログラムを作ることも目指しています。
橘🎤
たしかに、昔から脈診班では先輩が後輩に教えていましたね。
東垣🗣️
診断にとって重要な「脈診」を、みんなが習得できるように、
練習方法も研究を重ねながら作っています。
習得方法を日々の活動で模索しています。

橘🎤
これもみんなで練習している様子ですか?
東垣🗣️
そうです。手を当てる位置も重要ですが、
どうやってその位置を決めるか、
脈を押す指の力の入れ方なども練習しています。
脈をとる(診る)ためには・・
橘🎤
脈を診るのに大切なことはなんですか?
東垣🗣️
研究班のなかでは、1つ1つステップアップしていく形をとっています。
段階を踏んで、順序立てて、慌てずに習得していくことが大切です。
橘🎤
ステップアップ形式がポイントになっているのでしょうか?
東垣🗣️
その通りです。
1つのことがしっかりできるようになってから、
次のステップに進むのです。
手を使った技術ですから!
頭でわかったつもりでいることでも、
技術としてすぐに手を使ってできるとは限りません。
無意識でもできるようになるまで、
からだで覚えることが大切なのです。
橘🎤
そのために毎日コツコツできることはありますか?
東垣🗣️
もちろんです。
体調によって同じ人でも脈は大きく変わるものです。
毎日同じ人を継続して観察することも重要ですし、
自分の脈を日ごろからさまざまなシーンでチェックすることも重要です。
先輩から後輩へ

橘🎤
これはどんなシーンですか?
東垣🗣️
こちらは3年生が前に立ち、1年目のメンバーに、
脈診の習得方法を説明しているところですね。
橘🎤
そういえば1年目がみんな1年生とも限りませんよね。
2年生からでも3年生からでも、始められる時から参加してよいシステムですから。
東垣🗣️
そうです。
2年生(2年目のメンバー)は、フォロー役として、
研究班の活動を支えます。
もちろん教員が常に共に指導をしています。
みんなが共有できる表現や視覚化できるツールも探っています。
一つずつできることを増やして

橘
グループワークでは、このように各グループに分かれ、
上級生が指導します。
手の感覚を養うためには、毎日少しずつでも
脈に触れていくことがコツです。
学園祭では脈診班のコーナーがあり、脈をみてもらうことができますよ!
ぜひ体験してみてください。
脈診班の細かい活動はまた次の機会にご紹介いたします。